(電気通信設備工事共通仕様書 第8節)
1. 一般事項(第3-4-8-1)
施工上の基本ルール(損傷防止/張力管理/防水対策)
- 許容張力・許容曲げ半径・許容側圧を遵守(曲げは断線・損失の要因となるため厳守)
- 敷設中は、テンションメンバに延線用撚戻し金物(プーリングアイ)を接続し、ケーブル本体を直接引っ張らない
- 8の字取り: 延線困難・張力超過時に張力を分散する手法として用いる
- ケーブル端部に防水処置を施し、水分の侵入を防ぐ
- 外圧や衝撃の恐れがある部分は防護処置を施す
- ケーブルに踏圧や物の荷重がかからないように注意する
2. 光ケーブル地中配線(第3-4-8-2)
- 敷設前に管路の清掃・通過試験(マンドリルまたはテストケーブル使用)を実施し、管路の状態を確認する
- ハンドホールごとに人員配置し、連携して施工する
- ハンドホール内では、余長を十分確保し、固定金物には固定しない
- 災害時等のケーブル移動に際し、キンク(折れ曲がり)や断線が生じないよう配慮する
- 他電力線との離隔距離は法令(電気設備の技術基準の解釈、有線電気通信設備令)に準拠する
3. 光ケーブル屋内配線(第3-4-8-3)
- 光コネクタや光コードが接続されている場合は保護が必須
- 落し込み工法: フリーアクセス床等では、張力を加えずに丁寧に敷設する
- ラック固定間隔 ・水平部:3m以下 / 垂直部:1.5m以下 で緊縛
- 他ケーブルとの積み重ね箇所の耐圧対応
- 他のケーブルとの交差や積み重ねがあるため、ケーブルの耐圧縮強度に注意し、輻輳箇所については保護を行う。また、他の工作物と交差しないように施工する
4. 光ケーブル屋外配線(第3-4-8-4)
- 他工事でケーブルが上から圧迫されることを想定し、耐圧を考慮し、許容側圧を超えないように施工する
- 温度変化により収縮・膨張が起こるため、接続点近傍に余長を設ける温度変化対策として接続点に余長
- 直線緊縛はNGで、熱収縮対策としてケーブルの曲げや余長で吸収する
5. 光ケーブル架空配線(第3-4-8-5)
- 屈曲部では金車などを使用し、許容曲率(許容曲げ半径)内で施工する
- ケーブル繰り出しはドラム回転を制御し、電柱間のたるみを防止する
- 撚戻し金物を使用しない直接けん引はNG(必ず使用する)
- ケーブルの弛度は設計計算に基づき調整し、共架・添架の場合は既設電線に合わせる
- 離隔距離は、 他の架空配線、変圧器、建造物との接触防止を考慮する
6. 光ケーブル接続(第3-4-8-6)
- 接続方法は融着接続(アーク放電)または光コネクタ接続を用いる
- 接続損失:融着 0.6dB/箇所以下、コネクタ 0.7dB/両端以下
- 融着接続はJIS C 6841に準拠する
- 心線接続前に残線などで試験融着を行い、品質を確認してから本接続する
- 融着部は保護スリーブなどで補強し、機械的外力や環境(水、湿気、有害ガス)から長期に保護する
- 融着心線を収める屈曲直径は6cm以上とし、心線が突起部などに接触しないように収める
- 湿気・塵埃の少ない環境で作業を行う
構造分類の比較
| 種類 | 分岐性 | 撚り構造 |
|---|---|---|
| SZ撚り型 | スロット切断不要 | ジグザグ配置 |
| テープスロット型 | 切断必要 | ストレート配置 |
接地処理について
| ケーブル種別 | 接地要否 | 備考 |
|---|---|---|
| メタリック | 必要(片端接地) | 両端接地はループ電流の恐れあり |
| ノンメタリック | 不要 | FRP等構造により金属なし |
測定・試験項目
- 接続損失の測定(測定区間の両端から測定し、その平均値を採用)
- 伝送損失の測定(施工区間の伝送損失が所定の規格値以下か確認)
- クロージャーの気密試験(防水性能を確認するため、気圧を高めて試験)
- 外観確認(光ケーブルの外観損傷、ねじれ、整理状態、付属器材の正しい取り付けなどを確認)

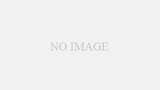
コメント